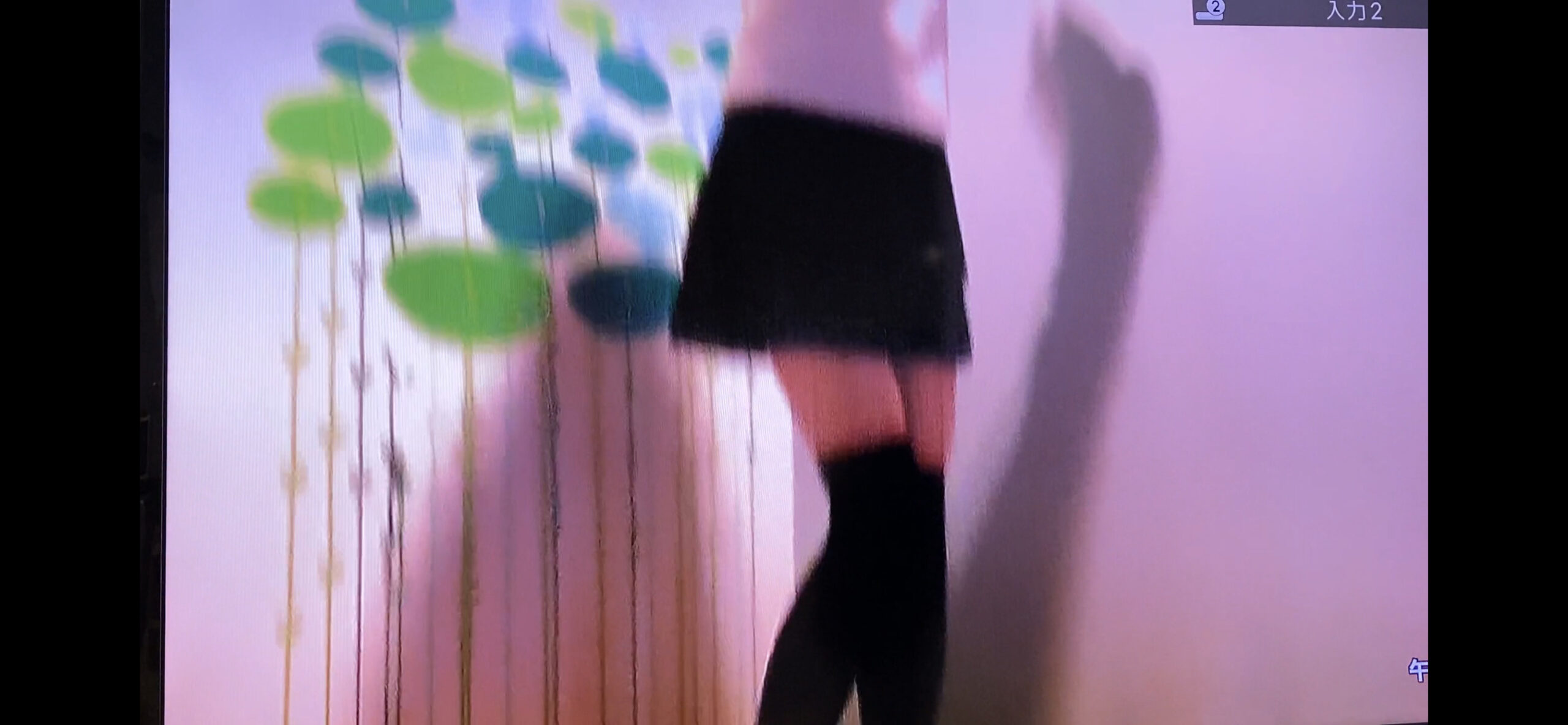これは10年くらい前のお話です。
彼女とはとあるイベントで知り合った。23歳女性。中堅商社でOLとして働く日々。164センチ、47キロでスタイルには申し分なし。お顔立ちも整ったクールビューティという形容があてはまるスレンダー美女だった。何よりも私の心を奪ったのは、足首周りの細さと脚全体のアライメント、修正のしようがない理想的な彼女の超絶美脚だった。


彼女と仲良くなった後、ある時にふと彼女に話を持ち掛ける。
私は趣味で映画撮影をしていて、こういう設定の作品を撮っている、こういう場面を撮りたくて貴女にぜひ出て欲しいです、と説明。設定はいつもの私が使うパターン。犯罪者がコオロギになる世界のお話。性的な要素は一切話していない。
もちろん無料で、とは言わない。それなりのギャラを提示。
最初はかなり訝しげな反応だったがこちらの必死ながらも誠実な対応に、次第に彼女のガードが緩むのを感じた。

春菜様「なんで私なんですか?? 誰でもいいですよね?」
私「この場面では貴女みたいな華奢な女性でも、小さな人から見たらとんでもない大きさであるという、そのギャップを表現したいんです。」

その時の私の表情はもう表現者のそれ、である。我ながらこの迫真の演技、ほめてやりたい。
最後には彼女も何の疑問も無さげな表情に変わった。
童顔で顔も小さくて切れ長のまつ毛、端正な顔立ち。普通にアイドルとか女優としてでもやっていけるんじゃないか?と彼女の表情を眺めながらふと思った。
後日やることにして、当日は(怪しまれるのも嫌だったので)こちらからは具体的な服装などは指定せず、彼氏とデートに行くとしてフェミニンな服装をお願いします、とだけ伝えた(実際に彼氏がいた)。
そして当日。待ち合わせ場所に彼女がやってきた。ミニスカートにニーハイソックス、ダイアナのおしゃれなハイヒール。かなり離れたところからもそのスタイルの良さがわかった。衝撃的なかわいさだった。こちらの予想のはるか上のレベル。ドМ足フェチから見たらとんでもない破壊力で、最初のうちはあまりの美しさに彼女をまともに見られなかった。もし10秒だけ誰にも気づかれずに自分だけ動けるとしたら、間違いなく這いつくばって彼女の靴を舐め回す自信がある。

それは女としての自分の武器がなんなのかを理解した完璧なスタイルだった。彼女のミニスカートとニーハイソックスの間の白くて細い太ももには一体どれくらいの価値があるのだろう。吸い込まれそうだ。もう犯罪で前科がついてもいいからとにかく触って顔をうずめたくなる。足フェチドМの冷静な判断を容易に奪う、とんでもないパーツだ。絶対領域という言葉を発明した人はノーベル賞の足フェチ部門をとるべきである。
落ち着け。興奮しすぎだ。
会場となったのは某カラオケボックス。少しお高くなるが、小さなステージのある部屋を借りた。この女性、顔良し、性格良し、スタイル良しで会社のいわゆる中年上司達からも好かれていて、接待には嫌でもよく連れていかれるらしい。カラオケで歌う曲もその世代に合わせている、という健気さが素敵である。そんな彼女が今回チョイスしたのはプリンセス・プリンセスの名曲「ダイヤモンド」。
さてスタンバイ。曲が始まる前に彼女の足元にはいつもの変態コオロギ達が陣取る。私達の誇り高き同志だ。彼らの視点になれたら死んでもいいと何度私は願ったことだろうか。目の前には巨大なハイヒール、細くてあまりにも長い2本の脚は漆黒のニーハイソックスに包まれて怪しく輝き理想的なラインを描いて天高くそびえる。その上に我々ゴミでは到底たどり着くことの叶わない女神の絶対領域、そして黒のミニスカート。間違いなく彼らのあの位置なら今日の彼女のパンティが見えるはずだ。私が彼らならそんなことを考えている。
おや、曲が始まった。

開始から華麗なステップ。彼女の中ではもう二次会のカラオケ、のノリである。何の躊躇もなく、彼女のカモシカのような細くて美しい脚を包む鋭いピンヒールが床にいる小さな観客に降り注ぐ。

彼らの悲鳴は大音量の曲と彼女の歌声にかき消されてしまい、撮影しているこちらには全く聞こえない。かろうじて彼女のステップするハイヒールの靴音が聞こえるだけだ。女神の足音で醜くそして黒くうごめく私達の分身は一瞬にして白い汁を出して別な何かに姿を変える。

サビが来た。もはや彼女は足元の惨状のことなど頭の片隅にもない(最初からなさそうだが、、、)。当たり前か、彼らがどうなろうと彼女には何の関係もない。どうでもいいのだ。カラオケの画面に夢中で、ノリノリで曲に合わせてジャンプを繰り返す。足元で命乞いをしている彼らは今、どんな気分なんだろうか?とんでもなく巨大なのに自分たちよりも遥かに速い動きで、しまいにはとてつもない高さから不可避な速度でせまるハイヒール。数グラムしかない彼らには一瞬も耐えることすらできない。そんな彼らに生き残れ!!というにはあまりにも理不尽な彼女の重さ。

ブチャ ブチブチ ピュピュ
もちろん撮影しているこちら側にはその音は全く聞こえない。しかし形容するならばそんな感じ、だろうか。誇り高き私の同志の最期の存在証明だ。その音は歌に夢中の彼女には全く届かなかったが、せめて、私達の記憶の中にだけでも刻みたい。

そんなことを考えながらうつぶせで撮影していた私の股間はあまりの絶景に耐えきれずに少し濡れたいた。

最後は女神の跳躍の下、美しいダイアナのハイヒールの近くで汚い汁だけが唯一映像に残されていた。